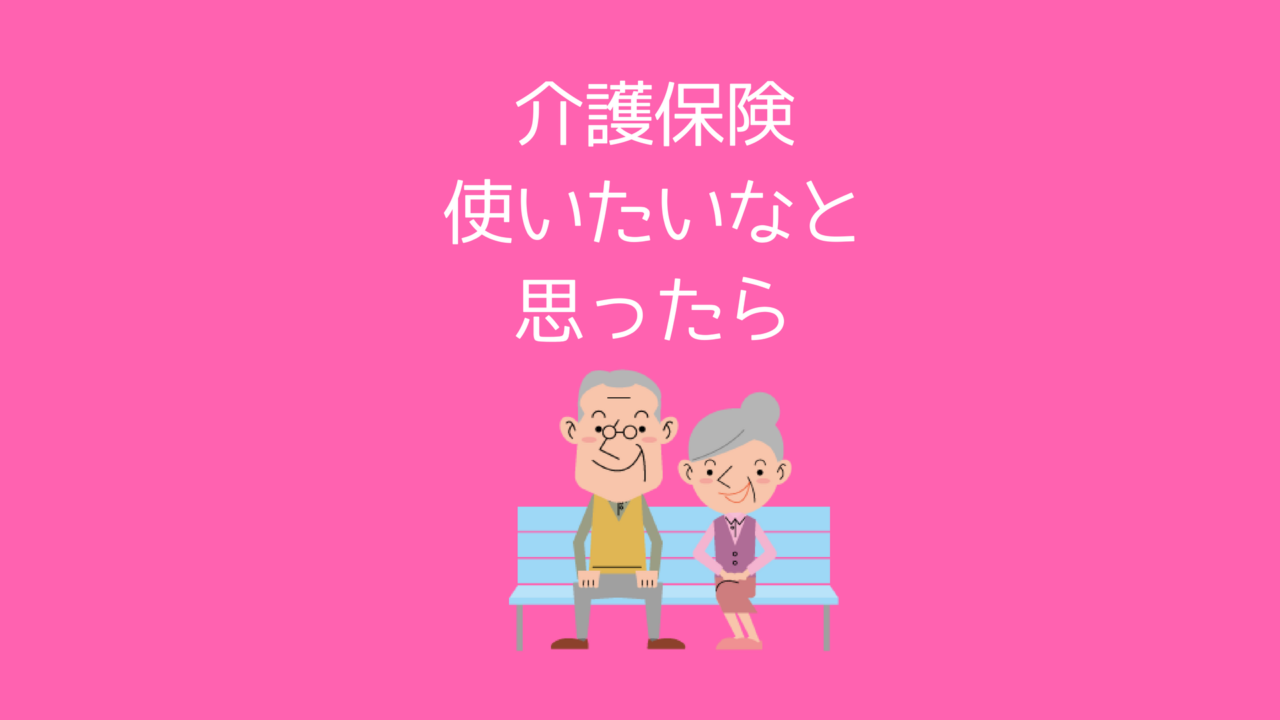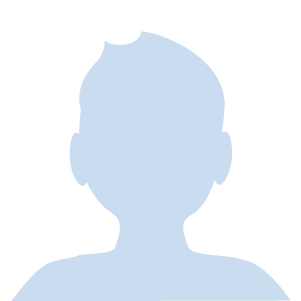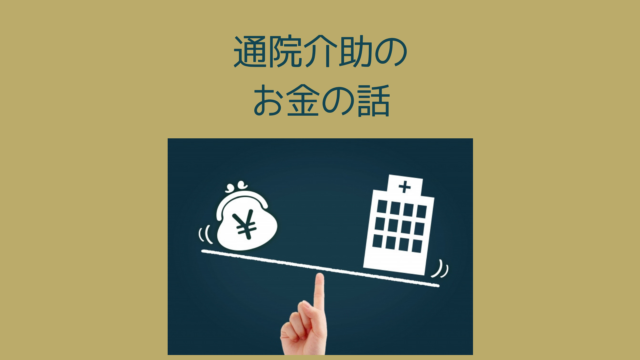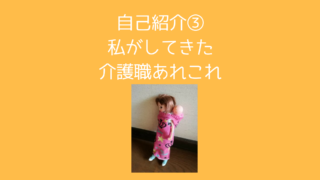介護保険でヘルパーやデイなどの介護サービスを使いたいなと思ったら、まず始めにお読みください。
介護保険という言葉は知っていても
・どう使えばいいのかわからない
・どんなことができるかわからない
そういった方向けの記事に仕上がっております。
いざそのときにならないと介護について考えることは少ないし、そしてその「いざ」のときには、早急な答えが求められてしまうので、何から手を付けていいのか、パニックになる方も少なくありません。
介護保険
その仕組みやできることを、いくつかに分けて、わかりやすくお話していきたいと思います。

目次(クリックするとその項目に飛びます)
そもそも介護保険を使って何ができるの?

まずはその申請方法。
65歳になると、保険者(多くは市町村)から介護保険証が送られてきます。
でも、この保険証が手元にあるだけでは介護保険は利用できません。
「介護保険を使って何かサービスを受けたいな」
そう思ったときに、
①介護保険証と書類を添えて役所に申請を出し
②介護保険認定調査を受け
③要支援1~要介護5までの何らかの結果が出て、初めて利用できます。
☞「介護保険でできること 介護保険のサービス一覧と簡単な説明」も読んでね。
なくても申請はできますよ
とにかく何か利用したい、そう思っても、要支援・要介護度が出ていなければ利用できないんです。
まずは役所に介護保険証と申請書類を出すところから始まります。
これに関しては自分で役所に行かなくても、地域包括支援センターでもいいですし、お近くの居宅介護支援事業所(居宅ケアマネのいるところ)で申請代行してくれますよ。
一番行きやすいところを選んで下さい。
そして現場の裏話としては、先々介護保険の利用を考えているならば、役所に行くよりも地域包括か居宅事業所に行って、申請代行を頼むついでに介護相談することをおすすめします。
そのほうが具体的な解決策を考えてくれます。
もし親身になって考えてくれなければ、その先結果が出たら、違うところに相談を持ちかけましょう。
☞「介護疲れにならないで 介護の悩みはどこで相談すればいいの?」
に介護相談の話を書いています。
介護保険を利用するにあたり、ケアマネ選びを間違えると本当に悲惨です。
上手なケアマネ選びはこちらのシリーズを☞☆☆☆☆
その後認定調査員から連絡があり、お互いの都合の良い日に認定調査を受けます。
これをミスるとすべてがおじゃん。
本気出さなくてはいけません。
上手な受け方はコチラに詳しく。
認定調査の時の主治医意見書って何?
この意見書の威力は絶大です。
調査内容とこの主治医意見書、二つをもとに要介護度が決まるわけですが、先生がのんきなこと書いていると、のんきな介護度しか出ません。
過去何回泣かされただろうか
何回調査結果を取り寄せて、先生こりゃないぜと泣かされただろうか。
ですので、介護保険の申請をする際には、必ず主治医の先生に
何をどう困っていて何のサービスを利用したいと思っているか
きっちりと話をしておきましょう。
それでも先生がのんきなことしか書いてくれなければ諦めるしかない。←
☞実際にご質問いただいたことを記事にさせて頂きました「要介護認定調査の時 主治医にうまく今の状況を伝えられなかった場合」
介護保険証が届いたらどうするか
そして大体申請から一ヶ月ほどしてから、要介護度を印字した介護保険証が届きます。
これが非該当(自立)であれば介護保険の利用はできません。
要支援1要支援2であれば
総合支援事業もしくは介護予防サービス
この違いの難しさは頭から火を噴いてもいいくらいなので、また詳しくお話します。(要支援のサービスの問題☞「介護保険の要支援の仕組みは複雑 要支援のケアマネ、訪問介護、デイ」)
要介護1~要介護5なら介護サービスを利用になります。
いえいえそうではありません。
申請日にさかのぼって介護保険の要介護度は適用されますから、例えば要介護1が出るかなと予想して、その範囲内でのサービスを申請日以降に利用することができます。
これを暫定ケアプランといいます。
暫定ケアプランについては別記事に詳しく書いていますが☞「暫定ケアプラン前中後編」
若干のギャンブル感は否めません。
ですから、要介護1くらい出るかなと思っていても、軽く見積もって要支援1程度しか出なかった場合の暫定プランを立てて動くことが多いです。
でも中にはそうもいかない人もいて、急に体調が悪くなってたくさんサービスがいるから、要介護3出るかもしれないなら、その範囲内でサービスを組んでくれという場合もあります。
もうケアマネ、結果来るまでドキがムネムネです。
結果次第ではとんでもない額の請求が来てしまうかもしれないですし。
なので、急を要しないのであれば、やはり然るべき結果が出てからサービスを利用する方がいいと思います。
以上簡単ですが、介護保険の申請のお話をいたしました。